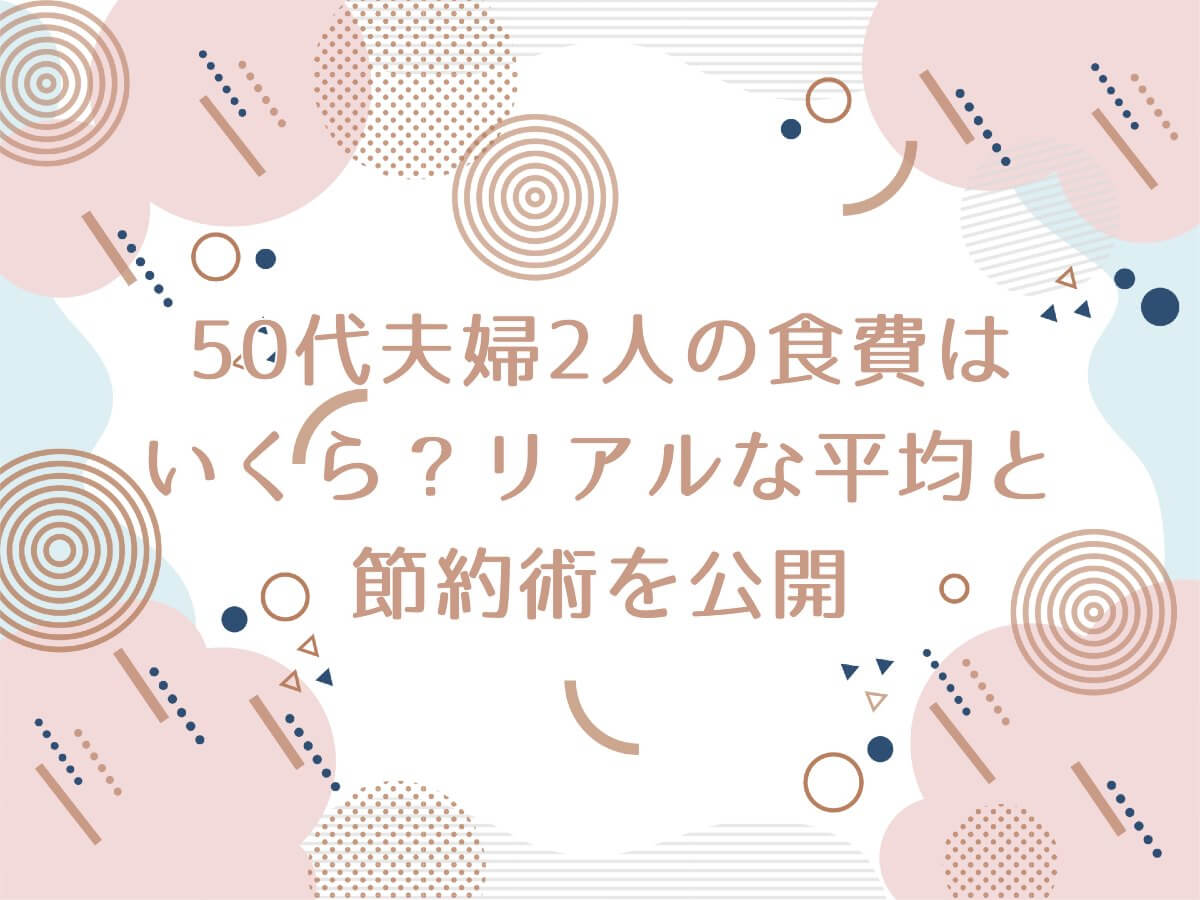50代夫婦2人暮らしの食費がどの程度かかっているのか、気になる方は多いのではないでしょうか。
この記事では、50代夫婦2人の食費について、平均額や実際の使い方、ライフスタイルによる違いなどを具体的に紹介しています。
たとえば、共働き世帯や専業主婦のいる家庭では、生活費の内訳や食費の配分も大きく変わってきます。
夫婦二人でお弁当を持参している場合や、外食を控えている場合など、それぞれのパターンに合わせた食費の目安も解説しています。
また1つ上の世代である60代夫婦2人の食費と比較しながら、50代夫婦の支出傾向にどんな違いがあるのかも丁寧に整理しました。
そして、二人暮らしで食費を3万円以内に抑えている家庭の具体例から、10万円を超えてしまうケースまで幅広く取り上げ、何がその差を生むのかをわかりやすく解説しています。
外食抜きでの食費の理想額や、エンゲル係数から見る家計バランス、食費を別々に管理する夫婦の実情など、実用的な視点で情報をまとめています。
50代夫婦の生活費平均の中で、食費をどうコントロールするか悩んでいる方や、これから家計の見直しを考えている方にとって、お役に立てていただければと思います。
記事のポイント
❷生活スタイル別の食費の目安
❸食費を抑える具体的な工夫
❹60代との比較で分かる50代の特徴
- 50代夫婦2人の食費はどれくらい?平均額とリアルな実態を解説
- 50代夫婦2人の食費を見直すポイントと節約の工夫
50代夫婦2人の食費はどれくらい?平均額とリアルな実態を解説
(画像)
- 50代夫婦の食費の平均額はいくら?統計データでチェック
- 夫婦2人の食費は平均と比べて多い?少ない?
- 夫婦2人でお弁当込みの食費は月いくらが目安?
- 50代の食費の平均とエンゲル係数の関係とは?
- 60代夫婦2人との食費の違いから見える傾向とは
- 夫婦で食費を別々に管理するメリット・デメリット
50代夫婦の食費の平均額はいくら?統計データでチェック
総務省の家計調査(2022年)によると、2人以上の世帯で50代にあたる家庭の1ヶ月あたりの食費の平均は83,984円です。
この中には外食やお菓子、アルコールなどの嗜好品も含まれており、自炊のみの食材費だけでなく、日々の生活に関わる幅広い食品費が含まれています。
外食費や調理食品の比率が高くなりがち
50代になると仕事の忙しさや体力の変化から、手軽に済ませられる調理食品や外食に頼る機会が増える傾向があります。特に共働きの家庭では、自炊の頻度が減ることで食費が上がりやすくなるようです。
家計調査によると、調理食品の支出は月1万円を超え、外食費も月7,000円以上と、食費全体の中でも大きな割合を占めています。
年齢別で見ると50代が食費のピーク
家計調査の年齢別データを見ると、50代は全世代の中でも最も食費が高くなる時期とされています。

ただし、これは子育てや教育費が一段落した家庭が多いことが背景にあるため、子どもがいない夫婦の場合には必ずしも当てはまらない可能性があります。
一方で、50代になると健康を意識して食材の質にこだわるようになったり、外食を楽しむ余裕が生まれたりするため、自然と食費が増えるケースもあります。
国産品や栄養価の高い食材を選ぶ傾向が強まるのもこの年代の特徴です。
参考までにエンゲル係数もチェック
家庭の支出全体に対する食費の割合を示す「エンゲル係数」も、50代夫婦の食費を考える上で参考になります。
2022年時点の平均エンゲル係数は約25.1%とされており、これは月25万円の消費支出がある場合、約6万3,000円が食費に充てられている計算になります。
自分たちの消費支出から食費の妥当性を判断する目安として活用できます。
夫婦2人の食費は平均と比べて多い?少ない?
夫婦2人で生活している中で「うちの食費は多いのか少ないのか」と悩む方は少なくありません。
食費の使い方には個人差が大きく、平均と比べて高いからといって浪費とは限りません。
ですが、全国平均と比べることで自分たちの食費の位置づけを知るヒントにはなります。
月6万円〜7万円程度は一般的な範囲
実際の生活事例から見ると、50代夫婦2人の食費は月に6万〜7万円が比較的多いボリュームゾーンです。
この金額には、日々の食材費に加えて、外食(月1〜4回)やアルコール、嗜好品なども含まれていることがほとんどです。
共働きで外食が多い家庭や、生協や宅配サービスを利用している家庭では、このくらいの金額になることは珍しくありません。
「多い」とされる基準は家庭の価値観で変わる
たとえば、夫婦で弁当を持参し、ほぼ自炊中心であれば食費を4〜5万円に抑えることも可能です。
一方で、外食が多く、食材にもこだわっている家庭では月8万円を超えることもあります。
大切なのは、収入や貯蓄の状況に見合っているかどうかです。
仮に月7万円でも無理なく生活でき、満足感のある食事が取れているならば「高すぎる」とは言えないでしょう。
平均と比較しながら自分たちの基準を見つけよう
周囲と比較して「高い・安い」と考えるよりも、自分たちのライフスタイルや収支に合った食費を把握することが重要です。
食事の内容、食材のこだわり、健康面への配慮、外食の頻度など、何にお金をかけているのかを意識してみると、自分たちにとって最適な食費が見えてきます。
夫婦2人でお弁当込みの食費は月いくらが目安?
50代夫婦2人の食費において、「お弁当を持参しているかどうか」は食費全体に大きく関わるポイントです。
特に共働きで昼食を外食に頼る場合、1人あたり1日1,000円前後、夫婦で月4万円以上かかることもあります。
一方で、自宅で用意したお弁当を持参すれば、1人1日200〜300円程度に抑えられ、2人合わせても月1.5万円程度で済むケースも多く見られます。
実際の食費モデル:自炊+お弁当生活の場合
お弁当込みで3食すべてを基本的に自炊している50代夫婦の場合、食費の目安は月4万〜6万円程度がひとつの基準になります。以下はその内訳の一例です。
- 食材費:月35,000〜45,000円(夕食中心に計算)
- お弁当分の追加食材:月5,000〜8,000円程度
- 嗜好品(コーヒー、おやつなど):月5,000円前後
このように、基本が自炊でお弁当持参というスタイルであれば、外食に比べてかなり食費を抑えることができます。
ただし、共働きで時間が限られている場合は、手間を減らすために冷凍食品やミールキットを取り入れることも多く、その分コストは上がる傾向があります。
外食や中食を多く取り入れるとどう変わる?
週に何度か外食を取り入れたり、コンビニ弁当やお惣菜などの「中食」に頼る頻度が高くなると、月の食費は6万〜8万円ほどになるケースもあります。
特に中食は1回あたりのコストが500〜700円程度と割高になるため、頻度が多いと家計への影響も大きくなります。
食費を抑えるには買い方と作り方の工夫が大切
お弁当生活を取り入れつつも無理なく食費を抑えるには、まとめ買いや冷凍保存をうまく活用し、余計な食材のロスを減らすことが効果的です。
また、お弁当の定番メニューをいくつか決めておくと、買い物も調理も効率的に行えます。冷凍野菜や作り置きおかずを活用することで、忙しい日でも継続しやすくなります。
50代の食費の平均とエンゲル係数の関係とは?
「自分たちの食費は高すぎるのか?」と感じたとき、目安となるのがエンゲル係数です。
これは、家計全体の支出に占める食費の割合を示す指標で、生活水準を考える際の参考になります。
2022年の総務省の調査では、2人以上世帯における50代の食費の平均は83,984円とされています。
エンゲル係数とは何か?
エンゲル係数は「食費 ÷ 消費支出 × 100」で計算されます。
たとえば月の消費支出が35万円で、食費が8万4,000円の場合、エンゲル係数は24%程度になります。
一般的にこの数値が高いほど、生活費における食費の割合が大きく、余裕の少ない家計とされます。
50代の平均的なエンゲル係数はどれくらい?
統計によると、2人以上世帯の平均エンゲル係数は約25.1%です。
収入が多い家庭では食費の割合が低くなりがちで、逆に収入が限られている場合は、食費の比重が大きくなります。
50代の夫婦世帯では、毎月の消費支出が35万円前後であれば、6万〜9万円の食費が一般的な範囲といえるでしょう。
収入やライフスタイルによって適正な割合は変わる
エンゲル係数は「食費が多い=悪い」というわけではありません。
たとえば、健康への投資として質の高い食材を選んでいる場合や、外食を楽しむことを生活の一部として取り入れている場合などは、食費が高めでも無理なく生活できていれば問題ありません。
大切なのは、自分たちの収入・支出バランスの中で無理のない範囲に収めることです。
エンゲル係数で見える家計の見直しポイント
エンゲル係数を目安にすることで、「実は外食が多すぎた」「コンビニ利用が増えていた」など、生活の中での無駄に気づけることもあります。
過剰な節約でストレスをためるのではなく、必要な支出と無駄な支出を見極めるきっかけとして活用してみてはいかがでしょうか。
60代夫婦2人との食費の違いから見える傾向とは
1つ上の世代である60代。50代と60代の夫婦2人暮らしでは、食費にどのような違いがあるのでしょうか。
総務省の家計調査によると、50代の食費の平均は約83,984円、60代では少し下がって約84,986円(55〜59歳)から82,527円(60〜64歳)となっています。
数字の差は大きくありませんが、食事への向き合い方や生活スタイルに変化が見られるようです。
自炊中心の生活にシフトする60代
60代になると定年退職などで時間に余裕ができ、外食よりも自炊を選ぶ機会が増える傾向があります。
スーパーの特売日を狙ったり、作り置きや冷凍保存を活用するなど、コストを抑えつつ健康にも配慮した食生活へと変化していきます。
これにより、実質的な食費が抑えられるケースが多く見られます。
食べる量の減少も影響
加齢にともない、1回あたりの食事量が減ってくることも、食費の変化に影響しています。消化に優しいメニューや小食傾向になることで、自然と購入する食材の量も減っていきます。
また、食材ロスを避けるために小分けでの購入や保存食品の活用も増え、結果として無駄な支出が減ることもあります。
健康志向の高まりで「選ぶ食材」は変化する
一方で、60代になると持病や健康リスクを意識して食材にこだわる家庭も多くなります。
塩分控えめの調味料や低脂肪のたんぱく源、無農薬野菜などを選ぶことで、品目単価は上がる傾向にあります。そのため、節約と健康志向とのバランスが、家計のなかで重要なテーマになってきます。
60代夫婦との比較で見える50代の食費傾向
50代夫婦はまだ仕事が忙しく、外食や中食(惣菜・弁当など)を利用することが多くなりがちです。
また「健康にも気をつけたいが、手間は減らしたい」という思いから、ミールキットや宅配食材サービスを使う家庭も多く見られます。
こうした利便性重視の食生活は、60代よりも食費が高くなる一因といえるでしょう。
夫婦で食費を別々に管理するメリット・デメリット
夫婦2人暮らしであっても、食費を「それぞれで管理」する家庭も中にはあります。
食費を別々にすることには、メリットもデメリットもあります。自分たちの生活スタイルや価値観に合った管理方法を見つけることが大切です。
メリット1:無駄な支出に気づきやすくなる
夫婦がそれぞれ自分の食事にかかる費用を負担する場合、「どのくらい使っているか」が明確になりやすくなります。
片方がコンビニや外食に多く使っていたり、嗜好品を多く購入している場合など、個人の消費傾向が見えやすく、改善しやすくなるのが特徴です。
メリット2:食生活の自由度が高まる
別々に管理することで、好きなものを自由に選びやすくなるというメリットもあります。
たとえば、夫は肉中心、妻は野菜中心といったように食の好みに差がある場合でも、ストレスを感じにくく、それぞれが満足する食事を取りやすくなります。
デメリット1:全体の支出が見えづらくなる
食費を分けていると、家庭全体での出費が把握しづらくなることがあります。
「夫婦で合わせて月いくら食費にかかっているのか」がわかりにくいため、家計管理全体が甘くなるリスクもあります。
共通の目標(貯蓄など)がある場合には、定期的な共有が必要です。
デメリット2:不公平感が生まれることも
別々に管理していることで、どちらか一方が一方的に家族全体の食材を多く買ってしまうと、不公平感を感じやすくなるケースもあります。
たとえば「自炊している方だけが調味料や共通の食材代を負担している」など、実際の食事量や使用分と金額が一致しないと摩擦が生まれることがあります。
どちらが良いかは家庭のスタイル次第
食費を別々にするか共同にするかは、一概にどちらが正解というわけではありません。
お互いの生活スタイルや働き方、食の好みに応じて、最もストレスの少ない形を見つけることが大切です。
定期的に話し合いながら、必要に応じて管理方法を見直していくのが良いと思います。
50代夫婦2人の食費を見直すポイントと節約の工夫
(画像)
- 外食を除いた二人暮らしの食費の理想額は?
- 50代夫婦の生活費の内訳から食費を見直すコツ
- 50代専業主婦の家庭における夫婦2人の生活費とは
- 二人暮らしで食費を月3万円に抑えるための工夫
- 二人暮らしで食費が月10万円になる原因とは?
- 50代夫婦の生活費の平均と食費のバランスを見直す
外食を除いた二人暮らしの食費の理想額は?
外食費を除いた食費、いわゆる「自炊中心の食材費」は、二人暮らしの場合どの程度が適正なのでしょうか。
住んでいる地域や食材へのこだわり、ライフスタイルによって差はあるものの、一般的な目安としては月3万円〜5万円の範囲に収まっている家庭が多いようです。
目安は月4万円前後がひとつの基準
自炊中心で生活している50代夫婦で、外食やコンビニ弁当をほとんど利用しない家庭では、月4万円前後の食費で十分にやりくりできるケースが多くあります。
これは1日あたり約1,300円、1人あたり650円程度にあたります。
献立を工夫し、まとめ買いや冷凍保存を取り入れれば、無理なく収まる金額です。
3万円未満に抑えている家庭も
さらに節約志向の家庭では、月2万〜3万円というケースもあります。
特売を活用したり、業務用スーパーを利用したりといった工夫でここまで抑えることも可能です。
ただし、この金額帯になると、ある程度の節約スキルと手間が必要になります。
5万円を超える場合は内容を見直すタイミングかも
外食なしでも月5万円を超える場合は、嗜好品や加工食品の比率が高い可能性があります。
夫婦で晩酌を楽しんだり、お菓子や飲料を頻繁に購入している場合には、支出がかさみやすくなります。
特に目的なく買っているものがあれば、見直すだけでも全体の支出は調整しやすくなります。
食材を使い切る工夫でロスを防ぐ
冷蔵庫内の食材を把握し、無駄なく使い切ることは、食費を抑えるための基本です。
月末に「買い足しなし週間」を設けたり、冷蔵庫の中身で献立を組む日を作ったりするだけでも、食材のロスが減り、コストダウンにつながります。
50代夫婦の生活費の内訳から食費を見直すコツ
生活費全体のバランスを見ると、食費が占める割合が高く感じることがあります。
実際の出費と比べることで、「使いすぎていないか」「もっと抑えられる部分はないか」といった見直しのヒントが見えてきます。
50代夫婦の生活費の内訳から、食費に着目して調整するポイントを考えてみましょう。
50代夫婦の平均的な生活費とは
総務省の統計によると、50代夫婦二人暮らしの消費支出の平均は約35万円前後とされています。
その中で、食費はおよそ8万7千円程度が目安とされており、これは生活費全体の約25%にあたります。
家計の中で食費は大きなウェイトを占めており、見直しの対象にしやすい部分でもあります。
まずは家計の「見える化」から
食費を調整したいときは、家計簿やアプリを使って、1ヶ月の支出を明確にすることから始めましょう。
食材、調味料、嗜好品、アルコール、外食など、できるだけ細かく分けて記録することで、無駄な部分や意識せずに使っていた出費が見えてきます。
固定費と変動費のバランスを考える
食費は変動費に分類される支出のひとつです。
一方で、住居費や通信費、保険料などの固定費は見直しが難しいため、食費のように調整しやすい項目に目を向けることは有効です。
無理なく減らすためには、1割削減など小さな目標から始めると続けやすくなります。
嗜好品やお酒の項目を独立させて管理
コーヒー、スイーツ、アルコールなどの嗜好品は、知らないうちに支出がふくらみがちな項目です。
これらを食材費と分けて管理するだけでも、「楽しみ」と「生活必需」の境界が明確になり、予算の調整がしやすくなります。
お酒があると月7,000〜1万円程度かかることもあるため、頻度や金額をあらかじめ決めておくのもひとつの方法です。
ムリのない予算でストレスの少ない節約を
「節約しなければ」と考えすぎると、食生活の楽しみが減ってしまいがちです。
大切なのは、無理のない予算の中で満足度を保つことです。
たとえば、食材は安く済ませても、月に一度の外食や、質の高い調味料を取り入れることで、全体としてはバランスの取れた支出になります。
50代専業主婦の家庭における夫婦2人の生活費とは
50代で専業主婦の家庭では、収入に限りがあるケースが多く、毎月の生活費はより現実的に計算される傾向があります。
特に夫婦2人だけの世帯では、子育てや教育費がかからない分、支出の内容もシンプルになります。ここでは、専業主婦のいる50代夫婦の生活費の特徴について見ていきます。
手取り30万円台がひとつの目安
夫が会社員で、手取り月収が30万〜35万円前後という場合、毎月の生活費はおおよそ25万〜30万円の範囲に収まることが多いです。
残りは貯蓄や将来の備えにまわす形になります。
生活費の内訳とそのバランス
生活費の一般的な内訳としては、以下のような項目があります。
- 住居費(賃貸またはローン返済):6万〜8万円
- 食費:4万〜6万円
- 水道光熱費:1万5千〜2万5千円
- 通信費:1万〜1万5千円
- 日用品・雑費:5千〜1万円
- 保険料:1万〜2万円
- 娯楽・交際費:1万〜2万円
このように、大きな変動のない支出が多くを占めるため、毎月の予算管理がしやすい反面、大きなゆとりを作るには計画的な支出が求められます。
食費は節約しやすい代表的な項目
食費は工夫次第で調整が可能な項目のひとつです。
専業主婦であれば、平日にまとめ買いをしたり、安いスーパーを使い分けたりすることで、コストを下げることができます。
また、自炊中心の生活スタイルであれば、無駄な出費を防ぎやすくなります。
ライフスタイルの変化に応じた支出管理がカギ
50代は老後に向けた準備を本格的に意識し始める時期でもあります。
大きな支出が落ち着いた今こそ、生活費全体を見直し、固定費を整理したり、保険や通信費の契約を見直したりする良いタイミングです。
収入の増加が見込みにくい分、支出の最適化が生活の安定に直結します。
二人暮らしで食費を月3万円に抑えるための工夫
「夫婦二人で食費を月3万円以内に抑えたい」と考える方は多くいます。
とはいえ、ただ節約するだけでは続かず、ストレスがたまりがちです。
無理のない工夫で、3万円以内に収めるためのポイントを紹介します。
買い物の回数を減らす
買い物に行く回数を週に1〜2回に抑えることで、無駄な出費を防ぎやすくなります。
スーパーに行くたびに余計なものを買ってしまうことは少なくありません。必要なものをリスト化し、まとめ買いを意識するだけでも支出はかなり抑えられます。
冷蔵庫の在庫を把握してから献立を考える
冷蔵庫や冷凍庫に何が残っているかを把握し、その食材を使い切る前提で献立を考えると、買い足しが少なく済みます。
「食材を使い切る日」を月に1〜2回作るのもおすすめです。特に野菜や肉類は冷凍保存を活用することで無駄を減らせます。
安い定番食材を味方につける
豆腐、もやし、卵、鶏むね肉、旬の野菜など、価格が安定していてコスパの良い食材をうまく取り入れると、食費を抑えながらもバリエーション豊かな食卓を作ることができます。
栄養バランスにも配慮しながら、食材の使い回しを意識しましょう。
外食と嗜好品のルールを決める
月3万円に収めたい場合、外食やアルコール、スイーツなどの嗜好品に関しては、頻度や予算のルールを事前に決めておくと安心です。
たとえば、外食は月1回、嗜好品は月2,000円までなど、あらかじめ枠を設定することで予算オーバーを防げます。
100円ショップや業務スーパーの活用
調味料や乾物などは100円ショップや業務スーパーで揃えるとコストパフォーマンスが高くなります。
必要な量だけを小分けで購入できる商品も多く、無駄なく使い切ることができます。使い勝手がよく節約にもつながるため、取り入れてみる価値はあります。
二人暮らしで食費が月10万円になる原因とは?
夫婦2人だけの暮らしで、食費が月10万円を超えてしまうというケースは決して珍しくありません。
ただし、それが継続していると「使いすぎなのでは?」と感じる方も多いのではないでしょうか。
月10万円という金額に達してしまう背景について考えてみます。
外食や中食の頻度が高い
食費が高くなる要因の中で最も大きいのが、外食や中食(スーパーやコンビニのお惣菜)の利用頻度です。
たとえば、週に3〜4回外食した場合、1回あたりの平均が3,000円でも月に3万円以上になる可能性があります。
中食も一見手軽ですが、1品あたりの単価が高いため積み重なるとかなりの金額になります。
嗜好品やアルコールの出費が多い
お酒やお菓子、コーヒー、ジュースなどの嗜好品は、習慣的に購入していると費用がかさんでしまいます。
特に夫婦どちらか、または両方がお酒を日常的にたしなむ場合、月に7,000円〜1万円程度かかることもあります。これだけで食費全体の1割近くを占めることになります。
無計画な買い物で食材ロスが発生している
買い物リストを作らずにその場の気分で購入する習慣があると、似たような食材を重複して買ってしまったり、使い切れずに捨ててしまったりすることがあります。
特に野菜や冷蔵品のロスは見えにくく、もったいない出費につながりやすいです。
高級食材やオーガニック食品の使用が多い
健康意識が高まり、良質な食材を選ぶようになると、1回の買い物あたりの単価は自然と上がります。
国産牛や天然魚、無農薬野菜などを日常的に購入していると、1週間で1万円以上かかることもあります。
もちろん、健康志向は大切ですが、全体のバランスを見ながら選ぶこともポイントです。
食に「満足感」を重視する傾向がある
50代の夫婦では、時間や気持ちに少しゆとりが生まれやすくなり、食事に対して「豊かさ」や「楽しさ」を求めるようになる傾向があります。
特に子どもがいない夫婦の場合、自分たちのペースで食生活を楽しめる分、食材選びや調理方法にこだわる方も多いようです。
たとえば、週末に少し高級な食材を取り寄せたり、全国のご当地グルメを取り入れて食卓を充実させたりと、食事をひとつの趣味や娯楽として楽しむスタイルが見られます。
そうした価値観が、食費が多めになる背景として表れることがあります。
50代夫婦の生活費の平均と食費のバランスを見直す
50代の夫婦2人暮らしでは、老後に向けた貯蓄を意識する時期に入りつつも、今の生活の満足度も大切にしたいと考える人が多くいます。
その中で、生活費全体のバランスを見直す際、食費が占める割合は特にチェックしておきたいポイントです。
50代夫婦の平均的な生活費と食費の割合
総務省の調査では、50代の夫婦2人世帯における平均的な生活費(消費支出)はおよそ35万円程度とされています。
そのうち、食費は約8万7千円前後で、全体の25%程度を占めています。この割合は、エンゲル係数とも呼ばれ、家計の中で食費がどの程度負担になっているかを表す目安になります。
エンゲル係数が高いと感じたときのチェックポイント
食費の割合が生活費の30%を超えている場合、食費に偏りすぎていないかを見直すサインとなります。
外食や嗜好品、調理済み食品の割合が大きくないかをチェックし、自炊や買い物の習慣を振り返ってみると、改善の糸口が見つかりやすくなります。
生活スタイルに合わせた調整が重要
共働きで忙しい夫婦であれば、多少食費が高くなるのは仕方のないことです。
一方で、専業主婦の家庭では、ゆとりを持って買い物や自炊の計画を立てることができるため、食費をコントロールしやすい環境にあります。
どちらのスタイルであっても、収入と支出のバランスを意識した生活設計が大切です。
食費を見直すことで貯蓄の余地が広がる
生活費の中で、食費は調整しやすい項目のひとつです。
月に数千円単位でも削減できれば、年間で見れば大きな差になります。
節約を目的とするのではなく、生活の質を落とさずに支出を最適化するという視点で見直すことで、より前向きに取り組めるようになります。
支出全体とのバランスを定期的に確認する
毎月の家計簿を振り返り、食費の割合や内容を確認する習慣を持つことで、無理のない調整がしやすくなります。
年齢とともに生活の形が変わっていく中で、支出のバランスも変化します。固定費と変動費を分けて見直すことで、生活全体の安定につながります。
【まとめ】0代夫婦2人の食費に関する傾向と実態
この記事のポイントをまとめます。
- 50代夫婦2人の平均的な月の食費は約83,984円
- 共働き家庭では外食や中食の利用が増え、食費が高くなりやすい
- 50代は全世代の中でも食費が最も高い傾向がある
- 子なし夫婦は食事に豊かさを求める傾向があり、食費に反映されやすい
- エンゲル係数の平均は約25.1%で、生活費の中でも食費の比率が大きい
- 自炊+お弁当持参での食費目安は月4万〜6万円程度
- 食材のまとめ買いや冷凍保存を活用すると食費を抑えやすい
- 外食やコンビニ利用が多いと月6万〜8万円に上がる傾向がある
- 節約家庭では月2〜3万円の食費でやりくりする例もある
- 食費が月10万円を超える家庭では外食や嗜好品の支出が多い
- 夫婦で食費を別々に管理することで自由度は増すが不公平感が出やすい
- 60代になると自炊中心にシフトし、食費がやや減少する傾向がある
- 専業主婦の家庭では買い物や自炊の工夫で食費をコントロールしやすい
- 生活費の見える化と分類で食費の無駄が見えやすくなる
- 無理なく節約を続けるには嗜好品の予算設定とバランスが重要

【関連記事】
・
・
・
・
↓よろしければこちらをポチッとお願いします↓